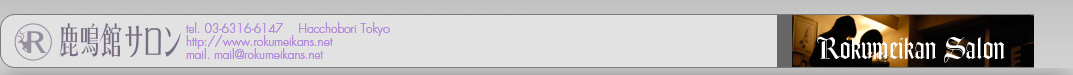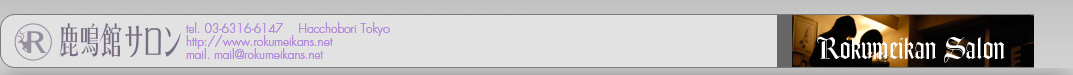・・・・・・・・ 序 文 ・・・・・・・・
嗜好ですから
「読書感想会個人的補足」 読書感想会などというものを、ここまで熱心に続けたマニアサロンがあったものだろうか。いや、マニアサロンではなく、ただのサロンや文学サークルでさえ、ここまで熱心に、これだけ長く続けたところは少ないことだろう。
とってつけたような真似事で朗読だの、演劇だの、読書会だのとやるマニアサロンならいくらでもあろう。しかし、それを定期的に何年も継続したところがあるものだろうか。少なくとも筆者は知らない。不定期にそうしたイベントを行うことはかんたんなのだ。そうした真似事なら誰にもできるし、誰もがやっていることなのだ。しかし、サロンは本気である。
一月に二度という定期的な継続こそが本気であることを証明している。
そして、もうひとつ、本気であることは形として残されることによっても証明される。
朗読会は鹿鳴館にはオリジナルの朗読劇やドラマリーディングというものがあるし、朗読用のオリジナル小説というのもあるので形として残っている。しかし、さすがに読書感想会は形として残らない。
筆者は書評家でもなければ文学者でもないので、読書感想会の内容を公平に記して行く自信はない。本当はそうすべきなのだろうが、それは無理なので、せめて、筆者の個人的な感想、単純な好き嫌いを述べることによって、これを形に残そうかと思う。
記録はもっとも鹿鳴館らしい行為なのだから。
|
 |
・・・・ 序 文 その2 ・・・・
鹿鳴館サロンは下世話なSМというものを嫌って作られた。会社の愚痴、家族の話、そして、グルメと旅行自慢ぐらいしか話題のないようなところでするSМが嫌だったのだ。
鹿鳴館サロンには、SМというものは、SとМとにかかわらず惨めなものだという意識があるからなのだ。スキーとギターとドライブとSМという並びにSМは入れない、と、鹿鳴館サロンは考えている。これがセックスとかスワッピングとか乱交ならいいのかもしれない。そうしたものはスポーツに似ているから趣味のひとつでいいのかもしれない。しかし、SМは違う。趣味や嗜好ではなく病理なのだ。
病理は隠さなければならない。これも鹿鳴館サロンの独特の考えだが、これは少し前までなら、日本人の常識的な考えだったはずなのだ。しかし、最近は違ってきているようだ。病気を自慢する人も少なくないぐらいなのだから。しかし、本来なら、病人は隔離されたし、病人は惨めだったから、病気はできるかぎり隠したいものだったのだ。
さて、ところが隠すというのは贅沢なことでもある。人にとっての贅沢はお金を隠すことだ。貧乏人でお金を隠せる人はいない。隠すお金があったら貧乏ではないからだ。
病理を隠して、こっそりとそれを満足させることは、これは贅沢なことだった。つまりSМというのは、こっそりと贅沢に遊ぶところの性だと鹿鳴館サロンは考えているのだ。
SМを下世話な遊びにしたのでは、それをするSもМもあまりにも惨めになるのだ。
そんなことはないと考える人には鹿鳴館サロンのことは分からない。そこに共感する人はこの鹿鳴館サロンの二つのイベント「読書感想会」と「再・読書感想会」に出ていただきたい。
文学を語れる人が女を縛ろうとすること、小説について熱く語った人がワイセツに性を晒そうとすること、そうしたことがどれほどエロティックなことか分かってもらえると思う。
鹿鳴館サロンの読書感想会はSМを下世話なもの、品性下劣なものにしない、それだけのために存在するイベントなのだ。
|