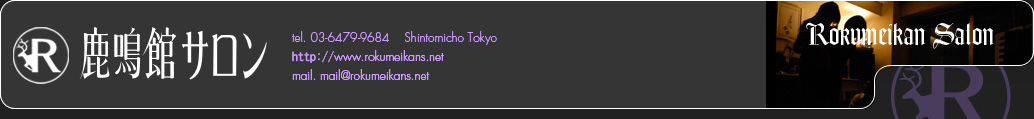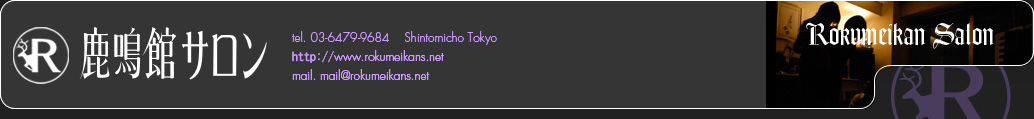可愛い女性の声だった。三人で行ってもいいかと尋ねられた。もちろん、断る理由はない。それからほどなくして、三人はやって来た。三人ともが女性だった。電話をかけてきた女性が三人のリーダー的存在なのだろうか、知らないサロンなのに、靴の置き場所から、廊下を歩く順番までを指揮していた。
「こういう場所なんだ、それじゃあ、ミキはそこ、ルミがそこで、私はここに座るから、あっ、一人二千五百円ですよね。みんな二千五百円払って何か注文して」
ミキと呼ばれる女性は三人の中でもとくに若く見えた。そのミキの前に飲み物を置くと同時に私の手に手錠がかけられた。もちろん、そうしたことは、このサロンではそう珍しいことではない。驚くこもせず、私は他の飲み物も作らなければならないから、と言ったのだが、誰れもはずそうとしない。私と手をつなぐことになった当人のミキさえ、それをはずして欲しいという態度がない。
そうした遊びにつきあうのも私のひとつの仕事と割り切り、不自由ではあるが、私は片手で残りの飲み物を作った。ミキも協力的だったので、それは、そう難しいことでもなかった。
「楽しいね」
リーダーっぽくふるまう女性が笑った。
「リエの好きそうなことだよね」
ルミと呼ばれた女性はそう言うと足を組み替えた。黒のミニの中に原色に近い真っ赤なパンツが見えた。それに気づいたのは私だけではなかった。
「すごい、ルミ、パンツ派手過ぎない」
「えっ、見えた」
「見せてるくせに。ねえ、ミキはどんなパンツなの、ちょっと見せて」
「えっ、私のは普通のですから」
このミキという女性には抵抗するという気持ちがないのか、リエがジーンズのベルトを外しにかかっても逃げようとしない。もちろん、片手は私とつながっているのだから抵抗しても、私が押さえるつもりではいたのだが、その抵抗さえしなかった。
「あっ」と、小さな声を上げただけで、ジーンズが膝まで下げられても、ミキは抵抗らしい抵抗はしなかった。恥ずかしいのか少し腰を後ろに引いただけだ。パンツは薄紫のレースで、若く見えるミキにはいささか地味に見えた。
まるで子供がされるようにジーンズを足から抜き取られても、ミキは平気だった。そうした命令に慣れているM女なのかもしれないと私は思った。女性同士のSM関係はもはや珍しいものでもなかったから、私は、ミキはリエの奴隷なのかもしれないと思った。
「さあ、乾杯しましょ」
ルミとリエは乾杯のために近づいた。二人の間の置かれていたミキのグラスは二人の向かいに置かれた。右手を私の左手につながれたミキはおそらくは利き腕でないと思われる左手でグラスを持った。
薄紫のパンツからうっすらと透けてヘアーが見える、そんな女が私と身体を密着させてお酒を飲んでいる、なんとも奇妙なものである。
「そろそろ、あの、他のお客さんもあるかもしれませんから」
「だって、もう、十一時ですよ。これから来る人なんていないでしょう。でも、もし、誰れか来たらはずしてあげるから、まだ、いいでしょ」
ああ、執拗に自分の遊びを貫く、いわゆる面倒なSタイプだと私は、そのときはじめて思った。
「いえ、その、ちょっとトイレにも行きたいので」
「だって、トイレぐらいできるでしょ。右手は自由なんだから」
トイレに行きたいわけではなかった。そう言えば手錠を外すかもしれないと思ったのだ。しかし、その気配はない。私は、そのままトイレに行くことに興味を抱いてしまった。露出の欲望が頭をもたげてしまったのだ。オシッコがしたいのだから仕方ないという理由で、ミキという女性にオチンチンを見せたい、そう思ってしまったのだ。
私のオシッコに付き合わなければならないのに、それにもミキは抵抗しなかった。
二人でトイレに向かった。私が便器に向かうためには、彼女はトイレの奥に入らなければならなかった。私は右手でファスナーをおろそうとしたが、うまくいかなかった。彼女に断り、少し左手を添えた。ペニスは勃ちかけたが、かろうじてオシッコを出せる程度で止まった。
「面白い、男の人のオシッコするところなんてはじめて見ました」
彼女は便器に落ちる私のオシッコを見て愛らしく笑った。その笑顔だけで、なぜか恋心を抱いていまう。単純なものである。
部屋にもどると、二人はクスクスと笑っていた。恋心を抱かせない笑いである。
「カギはこの部屋のどこかに隠したから。さあ、ミキは、下半身全裸になるのよ」
抵抗しない。パンツはルミが降ろした。ついでに私のパンツも降ろした。もう、抵抗しても仕方ないので、私は自由にさせておいた。三人の女性の前に晒されたからだろうか、私のペニスは何年ぶりかで勃起した。それを見て三人は笑った。笑われることは嫌ではなかった。
「じゃあ、私たちは、これで帰るから、終電までにカギを見つけてもらいなさい」
「本当にこのまま帰るんですか、冗談ですよねえ。まさか」
二人はクスクスと笑いながら上着を羽織った。本気のようだった。しかし、この時はまだ、私もそれがたいへんなことだとは思っていなかった。カギは単純に見つかるし、最悪なら降参の電話をミキが入れればいいのだと思っていたからだ。
しかし、カギは見つからなかった。終電の時間はとっくに過ぎていた。私たちは下半身全裸のままカギを探していた。何よりも先にカギだと思ってしまったからだ。
「私たちのパンツは」
カギを探す間も私のペニスは勃起していた。そのため、私の汁が彼女の太ももを汚してしまう。
「そうだね。先にパンツをつけようか」
と、その時、私たちは、自分たちのパンツが部屋にないのに気づいた。
「あっ」
洗面所でモーター音がする。洗濯機が回されているのだ。手錠につながれたまま洗濯機の蓋を開ける。中に私たちのパンツが入っていた。すでに洗濯が終りすすぎにはいっていた。
「仕方ない、このまま乾燥にして、その間にカギを探そう。最悪は泊まりになるけど、それはだいじょうぶなの」
「ええ、私は学生ですし、今は一人暮らしですから」
「よかった。コーヒーでも飲んで、少し落ち着いて、それから、カギを探そう。どうせ服が乾燥するまでには、時間がかかるからね」
「でも」
彼女はもじもじとしはじめた。
「あの、私、下剤を飲まされているんです。それが効いてきて、その、おトイレに」
たいしたプレイである。その場で浣腸され排泄されられることに比べたら、こんな状況で排泄させられることがどれほど恥ずかしいか、よく分かっているのだ。事実、彼女の顔は青ざめていた。便意をガマンしていたのだろう。SMプレイでもないのに、見知らぬ男の前で排泄しなければならないのだから、その羞恥は相当なものに違いない。
「私はスカトロ雑誌はたくさん作ってきたんですから、女性の排泄は見慣れているんですよ。気にすることはないので、トイレに行きましょう」
「すみません。でも、きっと、臭いですよ。耐えられないぐらい臭かったらどうしよう。あの、タオルとかでマスクをしてもらうとか、ああ、恥ずかしいです。こんな状況でウンチをしなければならないなんて。それに、下剤を飲まされているから、きっと、下痢しているかもしれません。おならもいっぱい出ちゃうかも。でも、カギが見つかるまでは、とてもガマンできなくて」
彼女は目に涙を浮かべていた。限界なのだ、便意も羞恥も。
私はトイレに彼女を連れて行った。下半身は裸なので、座ればいいだけだ。幸い、彼女の左に私が立てるので、今度はドアこそ閉められないがトイレの外に私の身体を逃がすことはできた。そんなことが彼女の慰めになるとも思えないが、私が奥にいなければならない状態よりは、いくぶんましだと私には思えたのだ。
「恥ずかしい。音も聞かれるんですね。ああ、でも、もう出ます。ガマンができないんです。本当にいいですか、出ますよ。出ちゃいますよ。いいですか」
悪いといって止まるような状態ではない。大きな破裂音が聞こえ、薄気味の悪い排出音が聞こえた。決して心地良い調べではない。
「苦しい」
そう言って彼女は両腕をおなかのところに抱えた。私はそれに協力したので、彼女の太ももに顔がついてしまった。吐き気がした。スカトロには慣れているものの、これほど近くでその匂いを嗅いだことはなかったかもしれないのだ。
「痛い」
彼女は肉体の苦痛のために、自分のおかれた羞恥の状態を忘れてしまったのだろう。膝を少し広げ体勢を楽にした。そのため、膝の間から、まさに今、彼女の体内から出て来たばかりのものが私の目に入ってしまった。
黒く長い固まり。それは下痢のときのものではなく、かなり健康そうな太さであり大きさだった。肛門までは見えないが、そこにぶら下がったまま、なかなか落ちない、その塊だけはハッキリと見ることができた。
鼻をつき、吐き気をともなった匂いには、慣れてきた。人間は匂いには慣れやすいのだ。
「だいぶ、よくなりました。すみません。そんな近くにいたら、ものすごく臭いですよね。あの、流してください。流しながらにしたほうが臭くないと思いますので」
「いや、でも、一度流したら、次は流れが悪くなるから、このまま出しきってしまったほうがいいですよ。もう私は匂いには慣れましたから」
彼女はほどなく便意からは解放された。しかし、羞恥から解放されることはなかった。
「こんな狭いところでは何だから、そのままお風呂で洗いましょうよ」
私は彼女をお風呂場に連れて行き、シャワーで汚れたお尻を流した。肛門に石けんをつけ、少し指を中に入れるようにして洗ったのだが、彼女はじっとしていた。
「さあ、部屋にもどろう」
私は濡れた彼女のお尻を拭きながら言った。
「あの、ずっと勃起したままなんですか」
「ええ、こんなエッチな身体を見せられ、オチンチンはすべすべの太ももに擦られるているし、この状況じゃあ、勃起はなかなか、おさまらないですよね」
勃起した私のものを彼女は優しく手で撫でた。そして、勃起したままでは疲れるでしょ、と、それに話しかけた。
たまらなく愛らしかった。私は彼女の股間に顔を埋め、そして、たった今、吐き気がするほど臭いものを出した穴のすぐそばの別の穴を舐めた。すでに興奮は頂点にあった。
正常位でインサートすると十代の頃のように、あっと言う間に射精してしまった。ギリギリでペニスを抜き、膣外射精するのが精一杯であった。
「すごい、たくさん。中でイッてくれても平気だったのに」
「そういうわけにもね。でも、ヘアーがベトベトになったから、また、シャワーだね」
「ええ、でも、今度は一人で浴びて来ます」
「いや、先にシャワーを浴びたほうが、カギがいつ見つかるかは分からないんだから」
「ごめんなさい。カギはポケットの中に、ほら」
にっこりと笑って、彼女は洋服の左ポケットから手錠のカギを出した。この笑顔だけは本当に愛らしいのだ。
手錠のカギを外すと、何が起こったのかよく分からない私を残し、彼女は風呂場へと向かった。
「乾燥も終わってたみたい」
明るい声が風呂場のほうから聞こえてきた。私はコーヒーを用意して彼女を待った。全ては彼女の企みだったのだろう。不愉快ではなかった。こんな遊びも面白いものだ。何よりも久しぶりでセックスまでできたのだ。不愉快どころか感謝したいほどだった。
鹿鳴館出版局 |